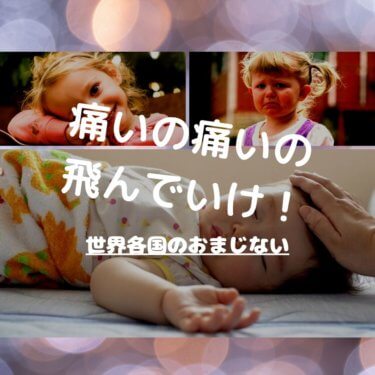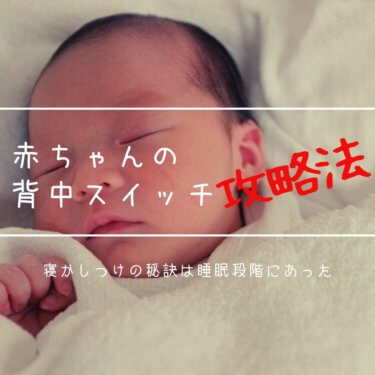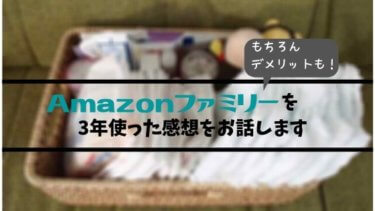最近公園に子どもを連れて行くと、
自分が子供だった頃とは設置されている遊具が
ずいぶんと違うな~と感じます。
私自身は30代後半なのですが、
我々の頃には当たり前だった、
「箱型ブランコ」 や「回転ジャングルジム」なんかは
仮にあったとしても、動きを制限されていることが
ほとんどです。
そんなことになっている理由は、国土交通省の
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」
によるものでした。
ここでは、消えた危険遊具で起こった事故や
上記指針についてまとめてみました。
消えた遊具たちと事故事例
これから挙げていく遊具が消えたのは、
やはり「危険だから」に他なりません。
ここではその代表的なものと、事故事例を紹介します。
回転ジャングルジム

事故事例 としては特に高速で回転させていた際に発生しています。
- 高速で回転させていたところ手を離してしまい落下し、負傷。
- 回転を止めようとして、遊具に手首が挟まり負傷。
箱型ブランコ

こちらの事故事例も勢いよくこぎ過ぎたために起こっています。
- 外からブランコを押していた子どもが、勢いあまって転倒し、戻ってきたブランコに頭を強打して死亡。
- ブランコが動いている状態から立ち上がったために転落し、ブランコと地面の間に挟まって負傷。
その他
その他にもシーソーや回転する塔など
特に動きのあるものの撤去が進んでいます。
その多くが、過剰に勢いをつけてしまったことや、
想定されていない姿勢で
使ってしまった場合に事故が起こっています。
遊具指針の作成
こうした事例を受けて、国土交通省は2002年に
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」
(以下、遊具指針)を作成しました。
遊具指針の位置づけ
この指針の位置づけとしては、以下のように記されています。
本指針は、都市公園において子どもにとって安全で楽しい遊び場を確保する
都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (改訂第2版) より
ため、子どもが遊びを通して心身の発育発達や自主性、創造性、社会性などを 身につけてゆく「遊びの価値」を尊重しつつ、子どもの遊戯施設の利用における安全確保に関して、公園管理者が配慮すべき事項を示すものである。
簡単に言うと、
公園の遊具を子どもに安全に使ってもらうために公園管理者が気を付けること
を示しますよ、ということですね。
動く遊具のどこが指針に合わなかったか
先ほど挙げた遊具は、この指針が定める
安全基準を満していないために設置されなくなったようです。
具体的には
重量が大きい可動性の箱型ぶらんこや遊動木などの遊具は、接触し た場合の衝撃が大きく、重大な事故につながるおそれがあるため、 選定に当たっては、想定される子どもの年齢構成や遊びの形態など について十分に考慮し、慎重を期する。
都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (改訂第2版) より
という部分でしょうか。
十分考慮し、慎重に期するということなので、
禁止とはしていないようです。
ただ
遊具の構造については、全体が子どもの利用に応じた強度を持つ必要があ り、特に、動きのある遊具では、全体の構造のみならず細部の構造についても 動きに対応した強度を持つように配慮するとともに、以下のような安全対策を 講ずる 。
都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (改訂第2版) より
とも記されていて、
- 絡まり・引っ掛かり対策
- 可動部との衝突対策
- 落下対策
- 挟み込み対策
- その他危険対策
を講じるよう定めたほか、使用する素材や、メンテナンスのしやすさ
などにも注意するように、としています。
このように細かい部分まで見ていくと、
箱型ブランコなどは対策ができている遊具とは言えない、
ということだったようですね。
まとめ
回転ジャングルジムや、箱型ブランコなどが
公園から消えた理由を紹介しました。
老朽化はもちろんあると思いますが、
国交省が発表した遊具指針に対して、
基準を満たせなくなったことが大きな原因です。
子どもは遊びの中で常に冒険・挑戦をします。
そのことが時には大人の想像を超える使い方を生み、
時には事故を引き起こしてしまいます。
近くで親が見ることができる間に、適切な使い方を
教えていくことも必要になってきますね。
今回の記事では指針の内容をかなり省略しましたので、
もっと細かく知りたい場合は、
引用部分のリンクから飛んでみてください。